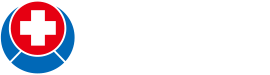この方法を習得するには、まだまだたくさんの時間と工夫が必要です。

(講習の様子から)
しかし当院のスタッフたちは、まず自分たちでできることから始めようと、
さっそく見よう見まねで、患者様と「出会いの準備」なることを行っています。
例えば、
いきなりカーテンを開けて、ベットのそばに行って話しかけるような
ことをしない。
壁をつかってノックを3回して、
返事があってからカーテンを開ける。
返事がなければ、3回その作業を繰り返してから名前を呼び、
患者様の視野の正面に入って3秒以内に「あなたに会いに来た」と
名乗りながら話しかける。
などです。
ケアをするときには、一人は常に患者様の顔の正面で話しかけ、
「これから○○をします」
「手を上げてください」
などと伝えます。
もう一人が黒子として、
説明に続いてその通りにケアを進めていきます。
今までケアをしていても固く身をこわばらせていた患者様が、
筋肉を緩めて身を委ね、笑顔で「ありがとう」と微笑んでくれる。
たったこれだけの事ですが、看護やケアのやりがいを
実感できているようです。
ケアをする人に誇りとやりがいを実感してもらう。
「人が尊厳をもって、住み慣れた地域で医療・介護をうけ、
その生をまっとうする」ことができる世の中になるために、
ユマニチュード®はすべての人々に希望を与えてくれる
メソッドだと思いました。
新年早々大変感動的な時間を共有することができ、
関係者の皆様、すべての皆様に感謝申し上げます。

(病棟での実習の様子 ※テレビの取材もありました)
※写真は一部修正しています。
「ユマニチュード®(Humanitude)」=Human(人)+Attitude(態度)を
組み合わせた造語(フランス語)です。
ユマニチュード®は、ケアをする人たちが認知症の人に接する際、
“人に接する態度”を徹底できるように考案された「具体的な技術」であり、
人の本質をつかんでいて国籍や人種に関わらず通じるため、
スイス・ベルギー他のヨーロッパ各国やカナダ・チリ・フィリピンなど、
国を超えて導入されているそうです。

(イブ・ジネスト先生)
認知症の人を「わからない人」のままにしない看護・ケアの重要性と
醍醐味に気づかせていただく。
この講演を聞いた人はみな、それぞれの職場で起こっていること、
日々葛藤していることを思い出し、目に涙が浮かんでくると言います。
【ユマニチュード®の基本となる4つの柱】
1.見つめること
2.話しかけること
3.ふれること
4.立つこと
ユマニチュード®の根底には「ケアをする人とは何か」「人とは何か」という
基本命題があり、この哲学に基づくケアの具体的な技術を学ぶと、
“当然できているつもり”であったことが実際には全くできていなかった
ことに気づかされます。
【優しさを伝える視線の技術】
1.垂直ではなく水平に
2.斜めからではなく正面から
3.一瞬ではなくある程度の時間
4.遠くからではなく近くから
「危ないからベッドで寝てて」「座ってて」
これは病院や介護施設だけではなく、ご家庭でも起きている
ことだと思います。
“寝たきり老人”を作っている、良かれと思って関わっている
私たちのそのやり方が「介護する人=暴力をふるう人」と思われて、
患者様・ご老人を攻撃的・あるいはその逆の低活動症候群に
させているということを教えていただき、目からうろこの思いでした。

(質疑の様子)
-「その3」に続く-
35年前にフランスで産声を上げた、認知症のケアメソッド「ユマニチュード®」を、
1月20日当院で勉強する機会をいただくことができました。

「ユマニチュード®」の提唱者の一人、イブ・ジネスト先生(フランス人)と
2011年単身フランスにこれを学びに行かれ、日本に持ち込まれた
本田美和子先生(国立医療機構東京医療センター総合内科)が
直々に当院にいらしてくださり、熱く語っていただくとともに、
その後実際にご入院中の患者さまとそのご家族のご協力のもと、
実習をさせていただきました。

先生方(左:イブ・ジネスト先生、右:本田美和子先生)
講演を聞いた当院の職員、地域の医療介護に関わる関係者の皆様
(診療所の先生・地域包括の方・市役所の方・他院の看護師さんなど)、
当院にご入院中の患者様のご家族の皆様が感動を味わい、
明日から自分たちでできることをやってみよう!という気持ちに
させていただきました。
実習では、患者様が最後に自ら手を上げて「ありがとう」と
おっしゃられるのを見て、いつもの患者様との違いに皆嬉しくなって、
思わず患者様を囲んで拍手でした。
-「その2」に続く-
1月21日(火)当院会議室にて、
「第5回 調布医療連携カンファレンス」を開催しました。
この会は、近隣の先生方と一緒に
よりよい地域医療を患者様に提供するため、
様々なテーマで行う勉強会で、
年に2度、開催しております。
過去の様子はこちら(クリックで開きます)
今回は中村ゆかり医師が司会を務め、
当院から以下の2つのテーマでお話しさせていただきました。
■Session 1: 生化10ケの落とし穴 ~測ってみましたナトリウム~
診療部 内科 熊谷 真義 医師
■Session 2: 腎不全保存期治療のポイント ~患者教育における多職種との連携~
診療部 内科 村岡 和彦 医師
医療技術部 栄養科 近藤 任子 管理栄養士
透析センター 看護部 西谷 令子 看護師
今回も25名程の地域の先生方がご参加くださいました。
また当院からは医師をはじめ、様々な部署から30名の職員が
共に学びの時を持ちました。

ご参加いただいた先生方からは、
「もっと聞きたい!」
「コメディカルの方々の顔を見ることができて良かった!」
といった、有り難い声を頂戴しました。
今後も、患者様や受診者の皆様にご満足いただける
質の高い医療を提供できるよう、
地域を挙げて取り組んでまいります。
お忙しい中、足を運んでいただいた皆様、
誠にありがとうございました。
次回も多くの方々のご参加をお待ち申し上げております。